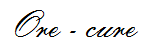
ふわふわと白雪が降りて足元を埋め尽くしていく。
暗闇に舞い積もる空からの来訪者はその姿同様儚いまま消え、その命が体を覆い重みを増す。
そっと掬いあげた僅かなそれは、留まることなく形を変え手の平に刺すような痛みだけを残していった。
あたたかさに触れ溶けてしまう、けれど完全に消え去ることのない姿に自分を重ねた。
思い出は消えてしまう。繰り返せば遠ざかっていく懐かしき日々。
真新しい雪は青白く寄り添い、あの人を想い浮かべた。
「綺麗な髪だ。輝いていて、触りたくなる」
白い髪の青年が微笑んで私の隣に座った。誰だかわからなかったけれど、白い髪の中に美しい青色を見つけた。
彼はブラーヴォと名乗った。思った通り青バラの一族だと告げ、それから毎日のように現れては話したり、時には森まで出かけたりして、いつしか一緒にいるのが当たり前のようになっていった。
彼は優しかった。勇気も強さもない私を怒ることも飽きることもなく、そばにいてくれた。そして多くを知っていて、年はあまり変わらないはずなのにまるで兄のように親身になって教えてくれた。
私は信じていた。この日々が永遠に続くのだと。
ある日彼は唐突に私の友人について尋ねてきた。
見かけて気になったという彼に、私は友人を紹介することにした。
「マリアン。赤バラ一族よ。マリアン、彼は……」
「青バラ一族でしょ?」
マリアンは彼を見るなりいつもの優しい声ではなく、信じられないものでも見るように目を見開いて踵を返そうとした。
「待って! マリアン、どうしたの」
追いかけようとした私の腕を彼が引っ張る。「いいんだ」とでもいうように彼は首を振って、困り笑いを浮かべた。
「慣れてるから。俺たち青バラ一族は認められてない存在だってこと、忘れてた」
存在さえ不可能とされた青バラ。奇跡が起きても、他のバラ一族はそれを快く思わなかったという。今でも続くその偏見に彼はいつも耐えてきたのだと胸がしめつけられた。
「マリアンは優しいの。きっとわかってくれる」
私は何度か二人が話をする機会をつくった。
マリアンの態度は相変わらずだったけれど、ブラーヴォは少し話ができただけでも嬉しそうに笑った。
「ねぇ、あの二人ちょっとお似合いじゃない?」
「あー……でも彼、青バラ一族でしょ? 絡まれてるんじゃない?」
「惜しいわね」
よく耳にするようになった会話。たしかに二人は美男美女で目を引くものがある。
種族の違いさえなければ、二人はもっと仲良くなれるのだろうか。
けれど生まれは決めることができない。できるのは、その偏見を無くすこと……どうしたら、二人は周りを気にせずにいられるのだろう?
そんなことを考え始めてから数日、二人がなぜか湖にいるのを見かけた。
声をかけようとして突風に思わず足を止める。おさまった頃再び湖の方を見ると、マリアンのリボンの付いた帽子が、湖畔にぷかぷか浮いていた。
そして何のためらいもなくブラーヴォが飛び込んで、その帽子を掴んで彼女に渡していた。
マリアンの様子から文句を言っているようだったけれど、彼女の白く長い手が彼に差し伸べられるのを見て、私はその場を走り去った。
あのときはわからなかった。今にして思えば、私は二人の心の距離が縮まるのを見ていられなくて逃げたのだと思う。
ブラーヴォが辛い思いをしないように、彼を理解してくれる人が増えるようにと願ってやまなかったのに。
私がいなくても二人はよく一緒にいるようになっていくのを見て、彼が構ってくれない寂しさよりも彼女への暗い感情に息が詰まった。
私は自分勝手だ。彼女は悪くない。種族ではなく彼自身を見ようとしてくれているのに、紹介しといて勝手に恨むなど……
震える手を押さえる。考えて考えて、思いを打ち消そうとした。
それでも残るわだかまりをどうすることもできずにいると、ブラーヴォが困ったように話をしてきた。
女性へのプレゼントは何がいいか――
「マリアンに?」
わかりやすく彼は動揺したので思い切って尋ねた。彼女のことをどう思っているのか、と。
結果はわかりきっていたものだった。
だから、私は彼に協力することにした。
焼き付いて離れない二人の姿。
そう、それから数か月経って二人の思いは通じ合った。
そのことで種族間の差別も少し薄らいでいて、二人は嬉しそうに寄り添いあった。
これから二人は明るい日差しの下、花の祝福を受ける。
けれど私は――そこにはいないだろう。
『綺麗な髪だ。輝いていて、触りたくなる』
優しく耳朶を打つ彼の言葉が木霊する。
『君がいるから…頑張れるんだ』
優しく包まれた手の温もり。
『いつもそばにいてくれてありがとう、ニゲル』
優しく頭を撫でる感触。
優しかった。どこまでも優しくて、だけど心の強い人。誰かのことを考えて自分まで傷ついている人だった。
彼の愛してくれた髪を梳く。ただ指を差し入れただけなのに束になって抜け落ちた。
氷鏡に映る色は彼の愛してくれた輝く銀ではなく、渦巻く思いを象るように漆黒に染まっている。
――天罰だ、と直感した。
人の幸せを妬もうとした私に、神が罰を与えたのだと。
それでもこれで良かったと思う自分もいた。
恨んでも悲しんでも二人は大事な人達に変わりない。
命はここで尽きるけれど、大好きな二人がこのままずっと私の分まで幸せになってくれれば……私は幸せ。このまま逝けるだろう。
けれど私は本当は――
〜end〜